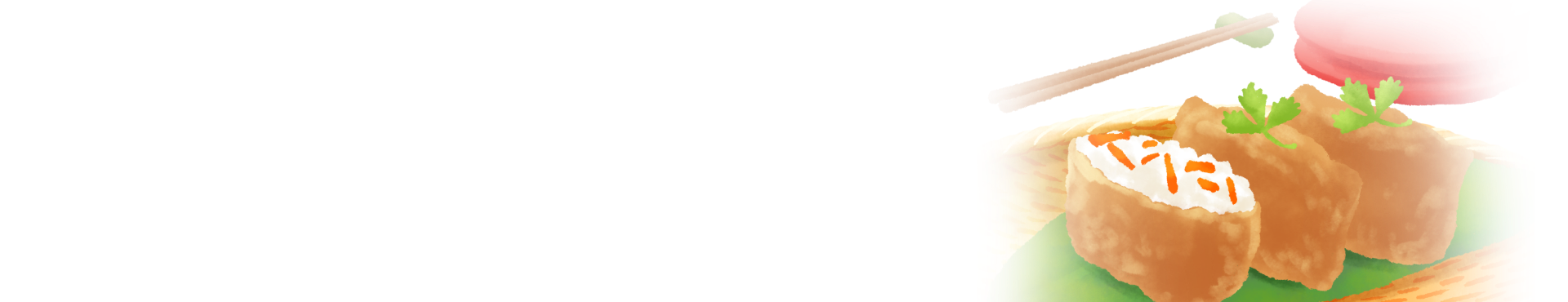お⽶のことなら何でも聞いて!
このコーナーでは、皆さまから寄せられたご質問等を元に、お⽶に関する様々な情報を発信していきます。
また「レシピ情報」のコーナーでは、お⽶をおいしく楽しめるレシピをたくさん紹介しています。
ここでは、お⽶の保存⽅法についてご紹介いたします。
-
お米を保存するときは、どんなことに注意したら良いですか?
乾燥
直射⽇光や空気にさらすと、お⽶がひび割れ、べちゃついたご飯の原因になります。
⽔濡れ
濡れた⼿で触れたり、温度差による結露(けつろ)などが発⽣したりすると、お⽶にカビなどが繁殖し、変⾊の原因になります。におい
お⽶は、においがとてもつきやすいので、洗剤や芳⾹剤、灯油、においの強い⾷べ物などと⼀緒に保存しないようにしてください。 シンク下での保存はにおいの原因になるため、避けてください。<保存状態をチェックしてみましょう>
- 直射⽇光は当たっていませんか?
- エアコンなどの⾵が直接当たり、乾燥状態になっていませんか?
- 近くで⽕を使ったり、電化製品の放熱で常に温かい場所だったりしませんか?
- 湿度が⾼く常にジトジト、ジメジメしている状態ではありませんか?
- 水に濡れる可能性がある場所ではありませんか?
- 周囲に強いにおいを発しているものはありませんか?
これらの中で1つでも該当していると要注意です!!
-
お⽶はどのように保存するのが良いですか?
お⽶の保存されるときは、乾燥や⽔濡れ、においうつりを防ぐためにも、密閉容器を利⽤し、冷蔵庫もしくは冷暗所で保存するのがおすすめです。
※密閉容器を使⽤する場合は、完全に乾かした状態で使⽤してください。
⽶びつでお⽶を保存する場合は、虫湧きを防ぐためにも、こまめに清掃し、古いお⽶を使い切ってから新しいお⽶を⼊れてください。
いろんなお⽶のおいしい炊き⽅をご紹介!
※炊飯器の操作や機能については取扱説明書をご確認ください。
-
炊飯器を使った「普通精⽶」のおいしい炊き⽅は?
- 計量
お⽶専⽤のカップで正確にはかってください。
※お⽶専⽤のカップは1合当たり約180ccで、重さは約150gです。
- 洗⽶
お⽶を⼊れた容器にたっぷりの⽔を⼊れさっとすすいで、⽔をすぐに捨てます。
⼿早く4〜5回洗ってください。
(この過程に時間をかけるとお⽶がとぎ汁を吸ってしまいヌカ臭くなることがあります。)
- ⽔加減
炊飯器の⽬盛にあわせてください。以後はお好みで調節してください。
※調理器具に⽬盛がない場合はお⽶1合カップ約180㏄に対し、⽔は約210㏄の割合です。
- ⽔に漬ける(浸漬時間)
30〜60 分、⽔に漬けてください。
- 炊飯
炊飯器のスイッチを⼊れてください。
- ほぐし
炊きあがったら、ご飯全体を軽くほぐしてください。
ほぐすことで、余分な⽔分が⾶んでおいしいご飯の出来上がりです。
- 計量
-
炊飯器を使った「無洗⽶」のおいしい炊き⽅は?
- 計量
お⽶専⽤のカップで正確にはかってください。
※お⽶専⽤のカップは1合当たり約180ccで、重さは約150gです。
- 洗⽶
とぐ必要はありませんが、気になる場合は軽くすすいでください。
- ⽔加減
炊飯器の⽬盛にあわせてください。以後はお好みで調節してください。
⽔を⼊れると多少⽩く濁ります。(これはお⽶のデンプンと気泡によるものです。)
※調理器具に⽬盛がない場合はお⽶1合カップ約180ccに対し、⽔は約220ccの割合です。
- ⽔に漬ける(浸漬時間)
30〜60 分、⽔に漬けてください。
- 炊飯
炊飯器のスイッチを⼊れてください。
- ほぐし
炊きあがったら、ご飯全体を軽くほぐしてください。
ほぐすことで、余分な⽔分が⾶んでおいしいご飯の出来上がりです。
- 計量
-
炊飯器を使った「胚芽精⽶」のおいしい炊き⽅は?
胚芽精⽶は胚芽部分を残してあるお⽶ですので、炊きあがりは茶⾊っぽくなりますが、特有の⾹ばしい⾹りや味があります。
※通常の⽩⽶と炊き⽅は変わりません。
- 計量
お⽶専⽤のカップで正確にはかってください。
※お⽶専⽤のカップは1合当たり約180ccで、重さは約150gです。
- 洗⽶
お⽶を⼊れた容器にたっぷりの⽔を⼊れさっとすすいで、⽔をすぐに捨てます。
⼿早く4〜5回洗ってください。
(この過程に時間をかけるとお⽶がとぎ汁を吸ってしまいヌカ臭くなることがあります。)
※無洗⽶の場合、とぐ必要はありませんが、気になる場合は軽くすすいでください。
- ⽔加減
炊飯器の⽬盛にあわせてください。以後はお好みで調節してください。
※調理器具に⽬盛がない場合はお⽶1合カップ約180㏄に対し、⽔は約210㏄の割合(無洗⽶では約220cc)です。
- ⽔に漬ける(浸漬時間)
3時間程度、⽔に漬けてください。
- 炊飯
炊飯器のスイッチを⼊れてください。
- ほぐし
炊きあがったら、ご飯全体を軽くほぐしてください。
ほぐすことで、余分な⽔分が⾶んでおいしいご飯の出来上がりです。
※胚芽精⽶は炊飯時に内蓋が汚れやすいので、炊飯後はお釜と⼀緒に都度洗うことをお勧めします。
- 計量
-
炊飯器を使った「⽞⽶」のおいしい炊き⽅は?
⽞⽶は昔から健康⾷として広く知られています。 ⽞⽶をおいしく炊くためには以下の⼿順を参考にしてくださ
い。
- 計量
お⽶専⽤のカップで正確にはかってください。
※お⽶専⽤のカップは1合当たり約180ccで、重さは約150gです。
- 洗⽶
⽞⽶についている汚れなどを取り除く程度に2〜3回洗ってください。
- ⽔加減
炊飯器の⽬盛にあわせてください。以後はお好みで調節してください。
※調理器具に⽬盛がない場合はお⽶1合カップ約180㏄に対し、⽔は約240㏄の割合です。
- ⽔に漬ける(浸漬時間)
3時間程度、⽔に漬けてください。
- 炊飯
炊飯器のスイッチを⼊れてください。
- ほぐし
炊きあがったら、ご飯全体を軽くほぐしてください。
ほぐすことで、余分な⽔分が⾶んでおいしいご飯の出来上がりです。
- 計量
-
炊飯器を使った「もち⽶」のおいしい炊き⽅は?
- 計量
お⽶専⽤のカップで正確にはかってください。
※お⽶専⽤のカップは1合当たり約180ccで、重さは約150gです。
- 洗⽶
お⽶を⼊れた容器にたっぷりの⽔を⼊れさっとすすいで、⽔をすぐに捨てます。
⼿早く4〜5回洗ってください。
(この過程に時間をかけるとお⽶がとぎ汁を吸ってしまいヌカ臭くなることがあります。)
- ⽔加減
お⽶1合カップ約180㏄に対し、⽔は同じカップ約180㏄の割合です。
- 炊飯
炊飯器のスイッチを⼊れてください。
※もち⽶は⽔に漬ける時間は設けず、すぐに炊きます。
- ほぐし
炊きあがったら、ご飯全体を軽くほぐしてください。
ほぐすことで、余分な⽔分が⾶んでおいしいご飯の出来上がりです。
- 計量
ご飯を炊飯器で⻑時間保温すると、⻩ばみやにおいが出たりします。
ごはんが残った場合には、冷凍保存をおすすめします。
-
ご飯を冷凍保存する⽅法は?
- 温かいうちにラップする
ごはんが温かいうちに、茶碗⼀杯程度の量を薄く平らにして、ラップでしっかり包みます。 - 粗熱を取ってから冷凍庫へ
粗熱を取ってから冷凍庫に⼊れてください。温かいうちに冷凍庫へ⼊れると、他の⾷材に影響がでます。
※冷凍保存したご飯は1か⽉を⽬安にお召し上がりください。
- 温かいうちにラップする
-
冷凍したご飯の解凍⽅法は?
レンジでチン!
お召し上がりの際は電⼦レンジで温めてください。
電⼦レンジから取り出す時は、やけどにご注意ください。
お⽶の外観について、お問合せがあった事例をご紹介いたします。
-
精米に白い粒が混ざっているのですが、何ですか?

- 拡大
- 粉状質粒(一例)
白っぽく見えるお米は、粉状質粒(ふんじょうしつりゅう)と呼ばれています。
粉状質粒は、お米が成熟していく段階で、天候の影響(主に高温障害)により発生するものです。
極端に多い場合を除き、食味への影響はありません。
栄養面、衛生面のいずれも問題はありません。 -
米粒に黒い点がありますが、何ですか?

- 拡大
- 着色粒(被害粒の一種)
虫による食害を受けて色がついた、着色粒(被害粒の一種)と呼ばれているものです。
例年ある程度の発生が見られ、選別機で除去していますが、色の濃淡や大きさによっては選別が困難な事があり、すべてを除去することはできないのが現状です。
見た目からご不快に感じる方もいらっしゃると思いますが、食味面、衛生面のいずれも問題はありません。
-
(胚芽精米又は玄米に)緑色の米粒がありますが、何ですか?

- 拡大
- 青未熟粒(一例)
青未熟粒(あおみじゅくりゅう)と呼ばれる粒です。
稲穂中の玄米は葉緑素があるため、元々は緑色をしています。この緑色は稲穂が成熟していくにつれて褪色していきますが、一部表皮に葉緑素が残ることがあります。
食味に影響はなく、数%の混入は適期刈取りの証拠ともいわれています。
異常なものではありませんので、ご安心ください。
-
お米ではない、黄色(又は茶色)の塊が入っていたのですが、何ですか?

- 拡大
- 糠玉(一例)
精米する時に発生する糠が固まったもので、糠玉(ぬかだま)と呼ばれています。
工場では定期的に清掃を実施し、選別機で除去していますが、糠玉はお米由来のものであるため色や成分が精米と酷似していて、除去しきれなかったものがまれに製品中に入ってしまう場合があります。
お米由来のものですので、ご安心ください。
-
お米が変色していてくさいのですが、なぜですか?

- 拡大
- 変色米(一例)
お米が何らかの要因で水分に触れて、カビや細菌が繁殖したためと考えられます。
発見された場合は、ご使用はおやめください。
※お米の袋には輸送時の破裂を防ぐため、小さな穴が開けてある場合があり、袋が濡れると中まで浸み込んでしまうことがあります。また、濡れた⼿でお米をすくったり、結露(けつろ)でお米が少量の水に触れた場合でも、変色することがありますのでお取扱いにはご注意ください。